
玉子巻繊蒸し(たまごけんちんむし)の語源、由来【和食の蒸し物 料理用語集】
玉子巻繊蒸し(たまごけんちんむし)とは、豆腐のかわりに玉子を使って「けんちん地」を作り、他の材料で巻いたり、包んだりして蒸した料理のことです。巻繊地(けんちんじ)とは、細く切った野菜を油で炒め、その中にくずした豆腐を入れて更に炒めたものです。■玉子で作った場合は「玉子けんちん地」といいます。
【日本料理の献立に役立つ参考書】和食の献立に必要な要素や四季折々の料理を項目、用途、月別にご紹介しております。松花堂弁当や茶懐石、会席料理など、毎月の献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

玉子巻繊蒸し(たまごけんちんむし)とは、豆腐のかわりに玉子を使って「けんちん地」を作り、他の材料で巻いたり、包んだりして蒸した料理のことです。巻繊地(けんちんじ)とは、細く切った野菜を油で炒め、その中にくずした豆腐を入れて更に炒めたものです。■玉子で作った場合は「玉子けんちん地」といいます。

蓮の葉蒸し(はすのはむし)とは、材料をハスの葉で包んだり、巻いたりして蒸し揚げた料理の総称で、れん根を使用した場合は「ハス蒸し」といいます。※ハスの葉は仏事に使うものとして敬遠されることがありますので、慶事料理の場合は注意してください。≫蒸し物用語一覧を見る

蓮蒸し(はすむし)とは、材料に「れん根」を使った蒸し物の総称で、葉を使用した場合は「ハスの葉蒸し」ともいいます。※ハスの葉は仏事に使うものとして敬遠されることがありますので、慶事料理の場合は注意してください。関連≫蒸し物用語一覧を見る
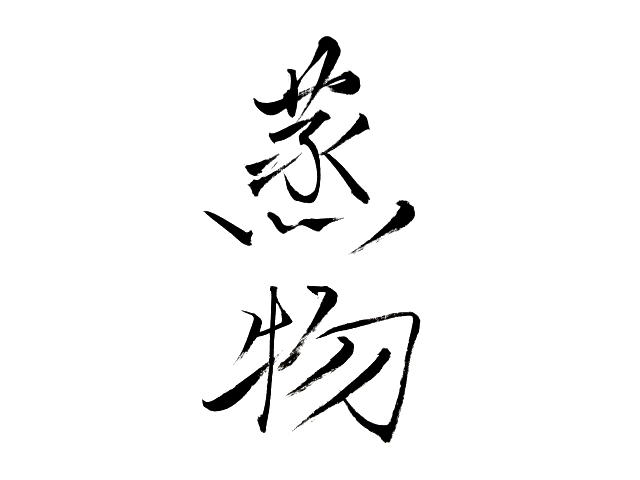
百草蒸し(ももくさむし)とは、複数の材料を使って蒸し上げた料理につける名称です。百草(ももくさ)とは、色々な材料を取り合わせた料理につける名称で、同じ意味で使われる献立名に千草(ちぐさ)があります。【関連】≫「千草蒸し」「千草焼き」

鯛の骨蒸し(たいのこつむし)とは、鯛の頭や中骨に塩をしたあと約30分間おき、昆布を敷いた器に並べて、だしを注いで蒸した料理のことです。豆腐や野菜類を一緒に蒸す場合もあります。

新茶蒸し(しんちゃむし)とは、4月~5月にかけてとれる、新しい茶葉を使った蒸し料理につける名称で、この葉は「一番茶」または「春茶」ともいいます。そして、蒸し物の例としては茶碗蒸しの玉子液に加えたり、もち米を蒸したものに混ぜたりします。また、他にも新茶を細かくつぶして葛あんに入れたり、白玉団子やおろし長芋に混ぜたりして使います。
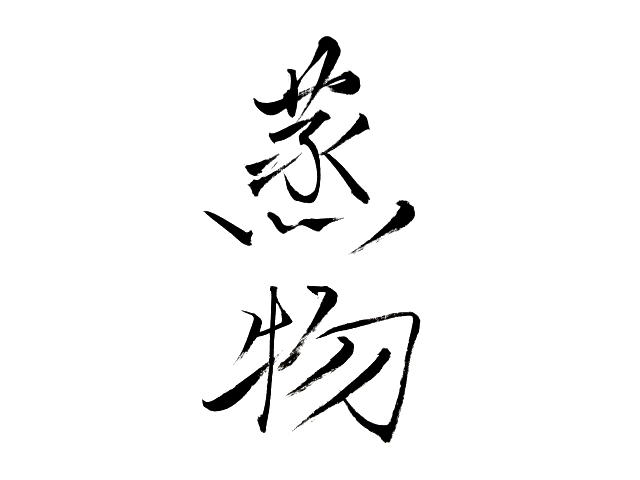
鳴門蒸し(なるとむし)とは、鳴門海きょうのうず潮に見立てた蒸し物につける名称で、形がうず巻き状になるように仕立てます。■魚肉ねり製品の「なると」と同じ意味の料理名で、蒸し物の他にも鳴門造りや鳴門焼き、鳴門煮、鳴門揚げなどがあります。また、鳴門地方が「わかめ」の特産地ということから、わかめを使った料理にこの名を使う場合もあります。
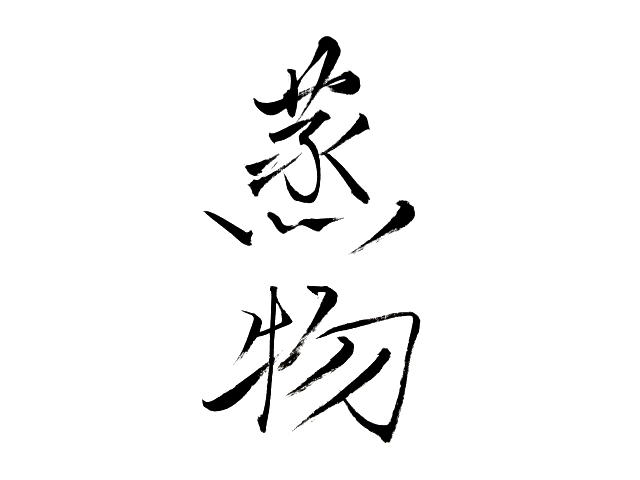
豊年蒸し(ほうねんむし)とは、穀物の豊作からつけられた料理名で、秋の献立に使います。もち米を蒸した「白蒸し」といわれるものを鶏肉や魚介類で包んだり、巻いたりして蒸す料理(飯蒸し)につける名称で、蒸し物の他にも豊年揚げや豊年焼きなどがあります。※食感を軽くする目的で、うるち米を使う場合もあります。
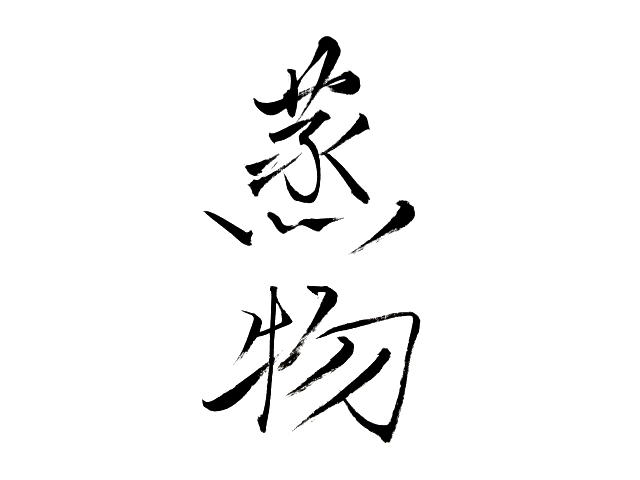
薯蕷蒸し(じょうよむし)とは、すりおろした山芋を白身魚や野菜、湯葉、そば等にのせて蒸した料理のことで「しょよ蒸し」ともいいます。また、薯用蒸し(じょうようむし)という場合もあり、具材にあるていど火を通してから山芋をのせて蒸し、仕上げに「調味だし」または「あん」をかけて香りのわさびやしょうがを添えます。
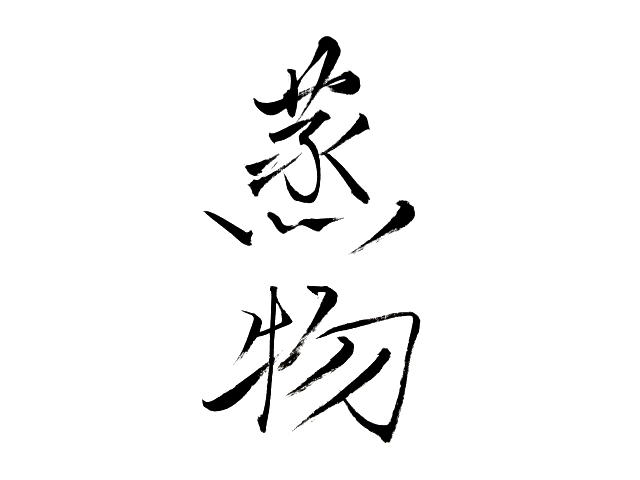
小田巻蒸し(おだまきむし)とは、うどんを具にした茶碗蒸しのことで「おだまき」と略す場合もあります。そして、この名は具のうどんを苧環(おだまき)に見立ててつけられた名称です。苧環(おだまき)とは、つむいだ麻糸をまるく輪に巻いたもので、献立に書く「小田巻」は料理名としてのあて字です。
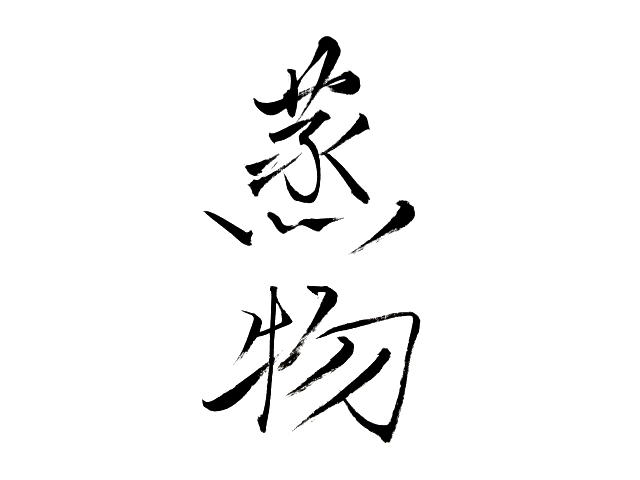
養老蒸し(ようろうむし)とは、すりおろした山芋を魚介類や野菜、そば等にのせて蒸した料理で、仕上げに調味だし、またはくずあんをかけて香りのわさびやしょうがを添え、薯蕷蒸し(じょうよむし)という場合もあります。また、すりおろした山芋を寒天で固めたものは「養老豆腐」といい先付け、小鉢、付き出しなどに使います。

巻繊焼き(けんちんやき)とは、けんちん地を魚や鶏肉で巻いたり、包んだりして焼いた料理のことです。巻繊地(けんちんじ)とは、細く切った野菜を油で炒め、その中にくずした豆腐を入れて更に炒めたもので、豆腐の代わりに卵を使ったものを「卵けんちん」といいます。

若竹蒸し(わかたけむし)の意味 和食の献立 蒸し物料理用語集 若竹蒸し(わかたけむし)とは 新タケノコと新ワカメを材料に使った春の献立...

具足蒸し(ぐそくむし)とは、えび、かになどをから付きのまま蒸した料理のことで、そのままでは大きい伊勢海老やかにをぶつ切り、筒切り、なし割りにしてから調理します。

重ね蒸し(かさねむし)とは蒸し物手法のひとつで、2種類、またはそれ以上の材料を重ね合わせて蒸した料理をいいます。【関連】博多蒸し(はかたむし)の語源、由来 ■蒸し物用語一覧を見る
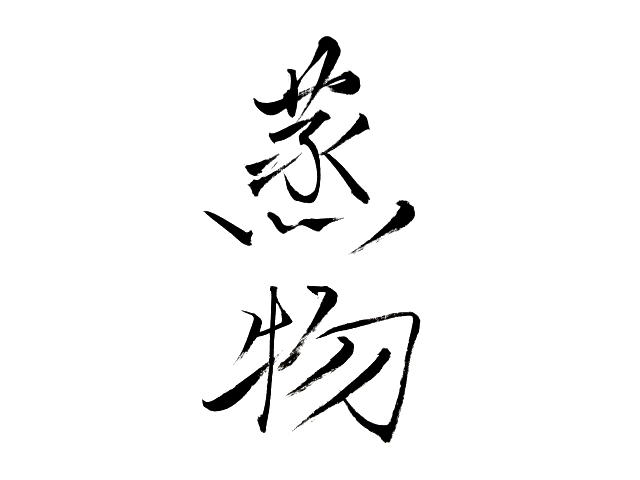
今回は丹波蒸し(たんばむし)の意味をご紹介したいと思いますので、蒸し物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。蒸し物の献立用語集、丹波蒸し(たんばむし)とは

鰻蒸し(うむし) 和食の献立 蒸し物料理用語集 鰻蒸し(うむし)とは 茶碗蒸しの一種。 ウナギのかば焼きを具に用いた蒸し料理のこ...

兜蒸し(かぶとむし) 和食の献立 蒸し物料理用語集 兜蒸し(かぶとむし)とは 魚の頭を蒸した料理のことで、タイ、アマダイ、ブリなどを用...
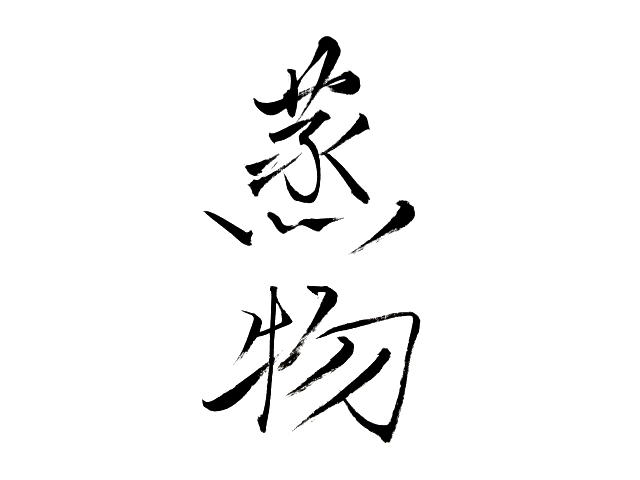
千草蒸し(ちぐさむし)とは、複数の材料を使って蒸し上げた料理につける名称です。千草(ちぐさ)とは、千草蒸しの他に「千草焼き」などがあり、色々な材料を取り合わせて調理した料理につける名称で、同じ意味で使われる献立名に百草(ももくさ)があります。

羽二重蒸し(はぶたえむし) 和食の献立 蒸し物料理用語集 羽二重蒸しとは 豆腐を使った蒸し物のことで、「羽二重」というのは舌ざわりよく...

蟹の甲羅蒸し(かにのこうらむし)の意味 和食の献立 蒸し物料理用語集 蟹の甲羅蒸しとは 蟹を使った蒸し物の献立のひとつです。 ほ...
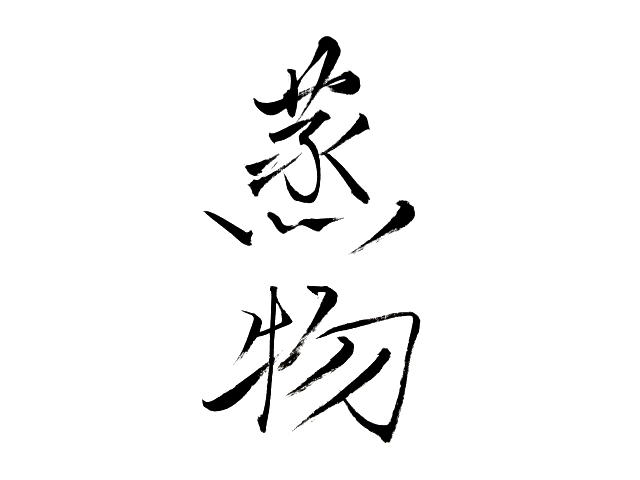
土佐蒸し(とさむし)とは、材料を土佐醤油に漬けてから蒸し上げた料理や、「かつお節」の旨味をきかせた蒸し物のことで、かつお節の産地が土佐(高知県)であることから、この名が使われます。

博多蒸し(はかたむし)とは、色が異なる材料を重ねて蒸した料理のことで、重ね蒸しともいいます。料理用語の博多とは

炮烙蒸し(ほうらくむし) 和食の献立 蒸し物料理用語集 炮烙蒸し(ほうらくむし)とは 焙烙(ほうろく)を用いた蒸し焼き料理のことで、「...