
10月のおしのぎ献立集【神無月の日本料理メニュー】
秋の献立、10月(神無月)お凌ぎの献立①焼き穴子ともち米の湯葉包み俵蒸し、吹き寄せ麩、針ねぎ、しょうがあん【関連】≫御凌ぎ(おしのぎ)の意味とは■白髪ねぎの切り方手順とコツ■野菜の飾り切り100選
【日本料理の献立に役立つ参考書】和食の献立に必要な要素や四季折々の料理を項目、用途、月別にご紹介しております。松花堂弁当や茶懐石、会席料理など、毎月の献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

秋の献立、10月(神無月)お凌ぎの献立①焼き穴子ともち米の湯葉包み俵蒸し、吹き寄せ麩、針ねぎ、しょうがあん【関連】≫御凌ぎ(おしのぎ)の意味とは■白髪ねぎの切り方手順とコツ■野菜の飾り切り100選

秋のお凌ぎ【10月の献立】今回は10月(神無月)の凌ぎを集めましたので、秋の献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

秋の献立【おしのぎレシピ】 今回は11月の御凌ぎ(おしのぎ)を集めましたので、献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。 11月の献立集...

秋の献立集【11月】今回は霜月のお凌ぎをご紹介したいと思いますので、秋の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。秋の献立【11月のお凌ぎ】関連≫「秋の食材50音順一覧表」

秋の献立集11月【お凌ぎ】今回は霜月の「お凌ぎ」をご紹介したいと思いますので、秋の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。秋の献立「11月お凌ぎ」①

今回は12月のおしのぎをご紹介したいと思いますので、冬の献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。12月のおしのぎ【師走】

冬の献立【師走のお凌ぎ】今回は12月のお凌ぎをご紹介したいと思いますので、冬の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。【関連】≫御凌ぎ(おしのぎ)の意味とは

今回は鯛を使った料理を3種類ご紹介したいと思いますので、春の献立やご飯物調理の参考にされてはいかがでしょうか。鯛料理の献立、御凌ぎ(おしのぎ)焼き鯛にゅう麺、桜葉寿司、鯛赤飯

今回は鯛を使った「お凌ぎ」を3つご紹介したいと思いますので、春の献立の参考にされてはいかがでしょうか。春の食材【鯛料理】お凌ぎの献立①焼き鯛赤飯蒸し、松葉しょうが、葉三つ葉、銀あん

春の御凌ぎ(おしのぎ) 米を使った春の献立3種 ≫御凌ぎ(おしのぎ)の意味 お凌ぎの献立① 鯛の昆布じめの小袖寿司桜葉巻き ...

春の食材と御凌ぎ(おしのぎ)の献立3種■お凌ぎの献立①鯛の昆布じめの小袖寿司■しょうがの甘酢漬け、花穂じそ、笹の葉■鯛の昆布じめの作り方■小袖(こそで)の意味■寿司に使える笹の葉の切り方■新しょうがの甘酢漬けの作り方と割合

今回は晩春から初夏にかけての御凌ぎ(おしのぎ)をご紹介したいと思いますので、和食調理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。

麺類の料理用語集【掛け蕎麦(かけそば)の名の由来】江戸時代の初め頃のそばの食べ方は、器に盛りつけた「そば」を箸で取り上げ、汁につけて食べるのが普通でした。ところが、人足(にんそく)達は、仕事の合間に立ったまま手軽に食べられるようにと、汁をそばにぶっかけて冷たいまま食べ始めました。

鴨南蛮とはアイガモのささ身とネギを使ったソバ料理のことで、ネギは煮ないで焼く、あるいは油で炒めたものを用いるところが特徴です。◆ネギを煮る場合は単に、カモソバ、またはカモネギソバといいます。料理用語の南蛮(なんばん)とは▶

小豆粥(あずきがゆ)とは、小豆を入れた「かゆ」のことで、1月15日の小正月を祝って食べる風習が今でもあり、元来は農耕神事としての習慣でした。別名【桜がゆ】

和食の献立【料理用語集】砧巻き(きぬたまき)とは桂むきにした材料で他の食材を巻いた料理のことです。調理例【胡瓜と白身魚のきぬた巻き】【焼き穴子と大根のきぬた巻き】≫焼き穴子と大根のきぬた巻きの煮物の作り方と調味料割合

小袖寿司(こそでずし)とは、小袖型にまとめた細めの棒寿司をいいます。小袖とは、着物のそでをかたどった切り方や形を模したもの、または普通よりも小さく作った料理につける名称で、小袖切り、小袖巻き、小袖かまぼこなどがあります。【関連】寿司の作り方関連一覧

赤飯蒸し(せきはんむし) 和食の献立 蒸し物料理用語集 赤飯蒸しとは 赤飯を使った蒸し物の総称です。 他の材料と一緒に加熱したり...

麺類の料理用語集【打掛(ぶっかけ)とは】掛け蕎麦(かけそば)の元になった言葉で、ぶっかけるという行為を表しています。【掛け蕎麦(かけそば)の名の由来】江戸時代の初め頃のそばの食べ方は、器に盛りつけた「そば」を箸で取り上げ、汁につけて食べるのが普通でした。ところが

温寿司(ぬくずし) 和食のご飯物、料理用語集 温寿司(ぬくずし)とは 提供する直前に温めた寿司の総称ですが、主に「蒸し寿司」と同じ意味...

鮎素麺(あゆそうめん) 麺類の料理用語集 鮎素麺とは 焼き鮎の身を素麺に盛りつけた料理のことで「おしのぎ」や、ご飯物がわりとして使いま...

桜寿司(さくらずし)とは、桜の形を模した細工寿司、または桜の花弁や葉の塩漬けを使って風味をつけた寿司のことです。■お凌ぎの献立一覧 ■ご飯物の献立一覧■寿司の作り方関連一覧へ

桜粥(さくらがゆ)とは 小豆粥の別名で、粥に小豆を入れると桜色になることから、この名があります。■小豆がゆの詳しい内容につきましては≫「1月15日に小豆がゆを食べる理由」に掲載しておりますのでお役立てください。
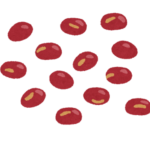
小豆粥(あずきがゆ)とは、小豆を入れた【かゆ】のことで、1月15日の小正月を祝って食べる風習が今でもあり、元来は農耕神事としての習慣でした。そして、別名を「15日がゆ」または「桜がゆ」といい、会席料理に使う場合は、お凌ぎやご飯物で提供するほか