
菊膾(きくなます)の意味【和食の献立、酢の物 料理用語集】
菊膾(きくなます) 酢の物の料理用語集 菊膾(きくなます)とは 菊の花を用いたなますのことで、ゆでた菊の花びらを加減酢や三杯酢、土...
【日本料理の献立に役立つ参考書】和食の献立に必要な要素や四季折々の料理を項目、用途、月別にご紹介しております。松花堂弁当や茶懐石、会席料理など、毎月の献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

菊膾(きくなます) 酢の物の料理用語集 菊膾(きくなます)とは 菊の花を用いたなますのことで、ゆでた菊の花びらを加減酢や三杯酢、土...

緑酢(みどりず)とは胡瓜(きゅうり)をすりおろして土佐酢や三杯酢などの加減酢と混ぜた合わせ酢のことです。【調理例】いかと鳥貝の緑酢■緑酢の簡単な作り方■土佐酢の調味料割合と作り方【関連事項】「蓼科酢(たてしなず)」「霙酢(みぞれず)」

今回は本サイトの【料理用語集】から、おろしたかぶや大根おろしを使った和え物につけられる名の霙和え(みぞれあえ)をご紹介したいと思いますので、献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。霙和え(みぞれあえ)とは、すりおろしたかぶや大根おろしを土佐酢、または加減酢などと混ぜ合わせて「おろし酢」を作り、和え衣として他の材料とあわせた料理をいいます。

海鼠腸和え(このわたあえ) 和え物の料理用語集 海鼠腸和え(このわたあえ)とは このわたに酒、みりん、卵黄などを混ぜ合わせて弱火で練り...

鮎算盤(あゆそろばん) 酢の物関連の料理用語集 鮎算盤(あゆそろばん)とは ① 鮎の頭を取って薄く筒切りにしたものに小麦粉、または片栗...

菜種和え(なたねあえ) 和え物の料理用語集 菜種和えとは ゆでて裏ごしした卵黄を和え衣に用いた料理のことで、その見た目から名がつけられ...

鮒算盤(ふなそろばん) 酢の物関連の料理用語集 鮒算盤(ふなそろば)とは ふなの頭を取って薄く筒切りにし、酢の中にしばらく浸けたあと大...

翡翠揚げ(ひすいあげ) 和食の揚げ物、料理用語集 翡翠揚げ(ひすいあげ)とは かわり揚げの一種で、ぎんなんを衣にして緑色に仕上げたもの...

和食の揚げ物、献立用語集【竜田揚げ(たつたあげ)とは】さば、鶏肉、白身魚などを酒、醤油、みりんを合わせた中に漬け込んで下味をつけ、葛粉や片栗粉をまぶして揚げた料理のことです。

料理の雑学、豆知識・うに揚げの意味!和食の献立、揚げ物料理用語集▶海胆揚げ・雲丹揚げ(うにあげ)とは?揚げ物の調理法、または献立名のひとつで、天ぷら用の衣に加工・・・

宇治揚げ(うじあげ) 和食の揚げ物、料理用語集 宇治揚げ(うじあげ)とは 色づけや香りづけに「ひき茶」を使用した揚げ物のことです。 ...

土瓶蒸し(どびんむし)とは、土瓶を使った蒸し物のことで、会席料理の献立では「吸い物代わり」として使う場合が多いです。※蒸し物として出すこともあります。

錦秋蒸し(きんしゅうむし)とは、色あざやかな蒸し料理に使う「秋の献立名」で、細切りにした数種類の野菜を白身魚や鶏肉などにのせて蒸し上げます。また、もみじ、いちょう、木の葉型に野菜を飾り切りして「吹き寄せ風」に仕上げた蒸し物にも使う献立名です。

蒸し物の献立用語集【錦秋餡(きんしゅうあん)とは】蒸し物や煮物にかけるあん(銀あん、べっこうあんなど)に、色とりどりの秋の食材を加えたものをいいます。秋の献立一覧【関連】錦秋(きんしゅう)とは

蒸し物の献立用語集【木の芽餡(きのめあん)とは】蒸し物や煮物にかけるあん(銀あん、べっこうあんなど)にたたき木の芽を加えたものをいい、春の献立に多く使います。「使用例」海老たけのこまんじゅう、木の芽あんかけ

今回は菊花餡(きっかあん)の意味をご紹介したいと思いますので、蒸し物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。蒸し物の献立用語集菊花餡(きっかあん)とは

蟹の甲羅蒸し(かにのこうらむし)の意味 和食の献立 蒸し物料理用語集 蟹の甲羅蒸しとは 蟹を使った蒸し物の献立のひとつです。 ほ...

甲羅蒸し(こうらむし) 和食の献立 蒸し物料理用語集 甲羅蒸しとは かにを使った献立のひとつで、茶碗蒸しに似た蒸し物です。 ほぐ...

桜蒸し(さくらむし)とは、食材を桜の葉で包んだり、桜漬けをのせて蒸した料理の総称です。一般的な桜蒸しは、薄紅色に染めた道明寺粉で白身魚や海老などを包んで桜の葉で巻き、これを「桜もち」と同じような形にして蒸し上げ、八方地や葛あんをかけて香りのわさび、おろししょうがなどを添えます。※桜漬けを混ぜ込んだ飯蒸しを桜蒸しという場合もあります。

焼き物、料理用語集【木の芽焼き(きのめやき)】木の芽焼きとは、魚介や野菜類の焼き物に木の芽をのせたり、たたき木の芽(包丁の刃でたたいたもの)を焼きだれに混ぜ合わせて仕上げにかけたりした料理をいいます。また、木の芽は山しょうの若い葉であることから「山しょう焼き」という場合もあります。

和食の焼き物【料理用語集】若竹焼き(わかたけやき)とは、材料にわかめと筍(たけのこ)を使った焼き物のことで、筍にわかめをのせて焼いたり、他の食材にわかめと筍を混ぜたものをのせて焼きます。
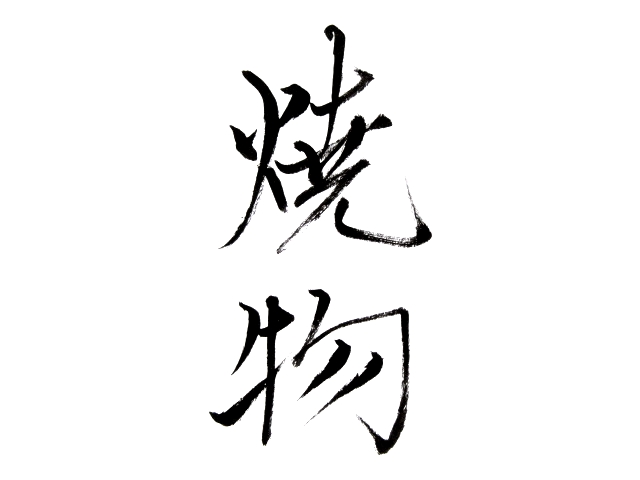
桜葉焼き(さくらばやき)とは、桜の葉で材料を包んで焼いたり、刻んだ葉を仕上げにのせた料理の名称で「春の献立」によく使います。
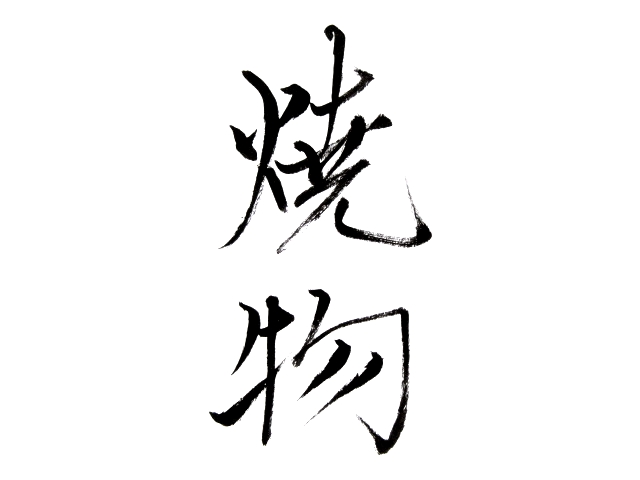
蓼酢焼き(たでずやき)とは、すりつぶした青蓼の葉と酢を混ぜ合わせて「蓼酢」を作り、材料にかけながら焼いたものや、蓼酢におかゆの裏ごしを加えて「蓼酢あん」に仕立てたものを焼き上がりに塗った料理です。
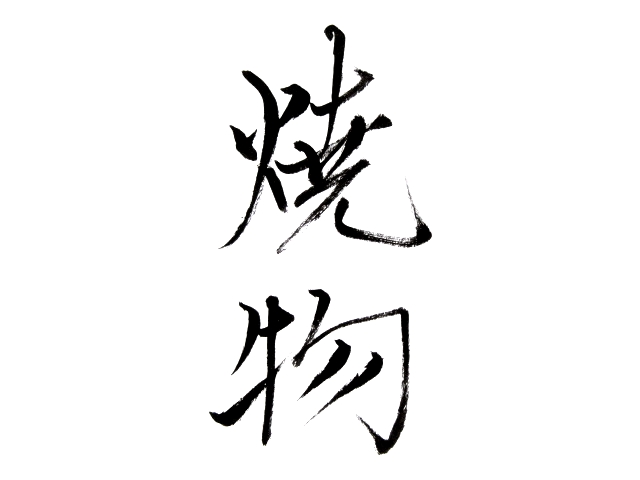
豊年焼き(ほうねんやき)とは、うるち米やもち米を使った焼き物の名称で、豊作を祝うという意味が込められています。【作り方の一例】魚、鶏、鴨などの中にもち米(白蒸し)を詰めたり、うす切りにした身で米を巻いたりして焼きます。また、揚げたものを豊年揚げといい、蒸し料理の場合は豊年蒸しといいます。